SIR ANDRÁS SCHIFF&
CAPPELLA ANDREA BARCA
Farewell Tour of Asia
Concert Report
サー・アンドラーシュ・シフ&
カペラ・アンドレアバルカ、
最後の来日公演を聴いて②
京都コンサートホールでの
モーツァルト
TEXT BY ATSUSHI ISHIKAWA, KAJIMOTO
PHOTOGRAPHS BY TATSUYA SHIRAISHI
サー・アンドラーシュ・シフ&カペラ・アンドレア・バルカ(CAB)の日本ツアー初日3/21は、ミューザ川崎シンフォニーホールでオール・バッハの鍵盤協奏曲。3日めの3/23は京都コンサートホールでオール・モーツァルト。その両方を聴きました。
オフィシャルレポート第1弾(川崎公演)はこちら

さてモーツァルト・プロの方は3/23、完全満席の京都コンサートホールです。
この日のシフとカペラ・アンドレア・バルカ(CAB)、J.S.バッハ・プロでの「アナログ感」は同じでも、今度のモーツァルトでは横の流れの繊細さ、美しさがとても印象的。そりゃあモーツァルトなんだから…と思いながら、それでもこの変わり方には虚をつかれたと言いますか、新鮮でした。シフもバッハの時と違って、オケのみの部分では立ち上がって優しくも精力的に指揮していましたし。
冒頭の「ピアノ協奏曲第23番イ長調K.488」において、きわめて自然な流れの中でピアノはフレーズごとに色を変え、歌ったり立ち止まったり、実に自由。弦楽は堅固なアンサンブルというより、パート毎にふわっと重なったり対話したり、そこに冴えた木管楽器群が花を咲かせたり、なんて愉快でしょう!普通はホモフォニックに思われるモーツァルトから、あたかもパレストリーナ風(?)なふんわり調和したポリフォニー(対位法)が聴こえるなんて…。
そして第2楽章の一種ロマンティックで感傷的な沈潜と、フィナーレの決して速すぎない喜びの発露のコントラストが何とも気持ちのいいこと。
それがまた、まるで最後のピアノ協奏曲である変ロ長調K.595のように儚く浮遊するかの佇まいがあり、思わず涙が滲みました。











続くオール・リピートの交響曲第40番。シフがピアノを弾かずに指揮だけをするのを見る貴重な機会です。
要所で引き締めることや、劇的な部分と穏やかな部分の交替やコントラストに重きを置いたシンプルな指揮ですが、ここでも一曲目同様、ポリフォニックな要素、それによって移り変わる音楽の色合い――もちろんこのト短調の曲はどうしたって悲劇的な様相をもちますが――を重視してたように思います。そこは1曲目同様・・・であっても全く違う厳しい風の吹きすさぶ世界。

後半の「ドン・ジョヴァンニ」序曲から「ピアノ協奏曲第20番K.466」へニ短調で繋ぐ―― 序曲の終わりの和音から間を置かずに協奏曲を始め、さらに協奏曲の第3楽章のカデンツァでは「ドン・ジョヴァンニ」序曲を使った即興を織り交ぜ、統一を強める離れワザ!―― 闇の深さはさらに違った世界。聴き慣れた曲でも、ドイツ語で言う“デモーニッシュ”とはこういうことかと震駭させられます。シフのピアノの冴え、音楽がピアニストの身体を通して直接聴こえてくるような大家ならではの力やエネルギーはもちろん、CABの名人たちが織りなす旋律線の彩をティンパニが締めるさまが、聴いてるこちらの気持ちをも引き締めてくれるような。オーケストラにおけるティンパニの重要性を痛感します。そうして、それがほかの声部を支えて統一を図るさまは、少し飛躍しますが、プロ前半と後半への流れがあたかもルネサンスのポリフォニーからバロックへ移り変わっていった音楽史を見るような…。
今度もまた前回の来日同様、シフとCABはルーティンな慣習などを削ぎ落として、作曲家の裸身を見せてくれました。少なくとも私にはそんな思いがしました。初日のバッハもこの日のモーツァルトも、磨き上げた美しさより内奥から現れる美しさ。
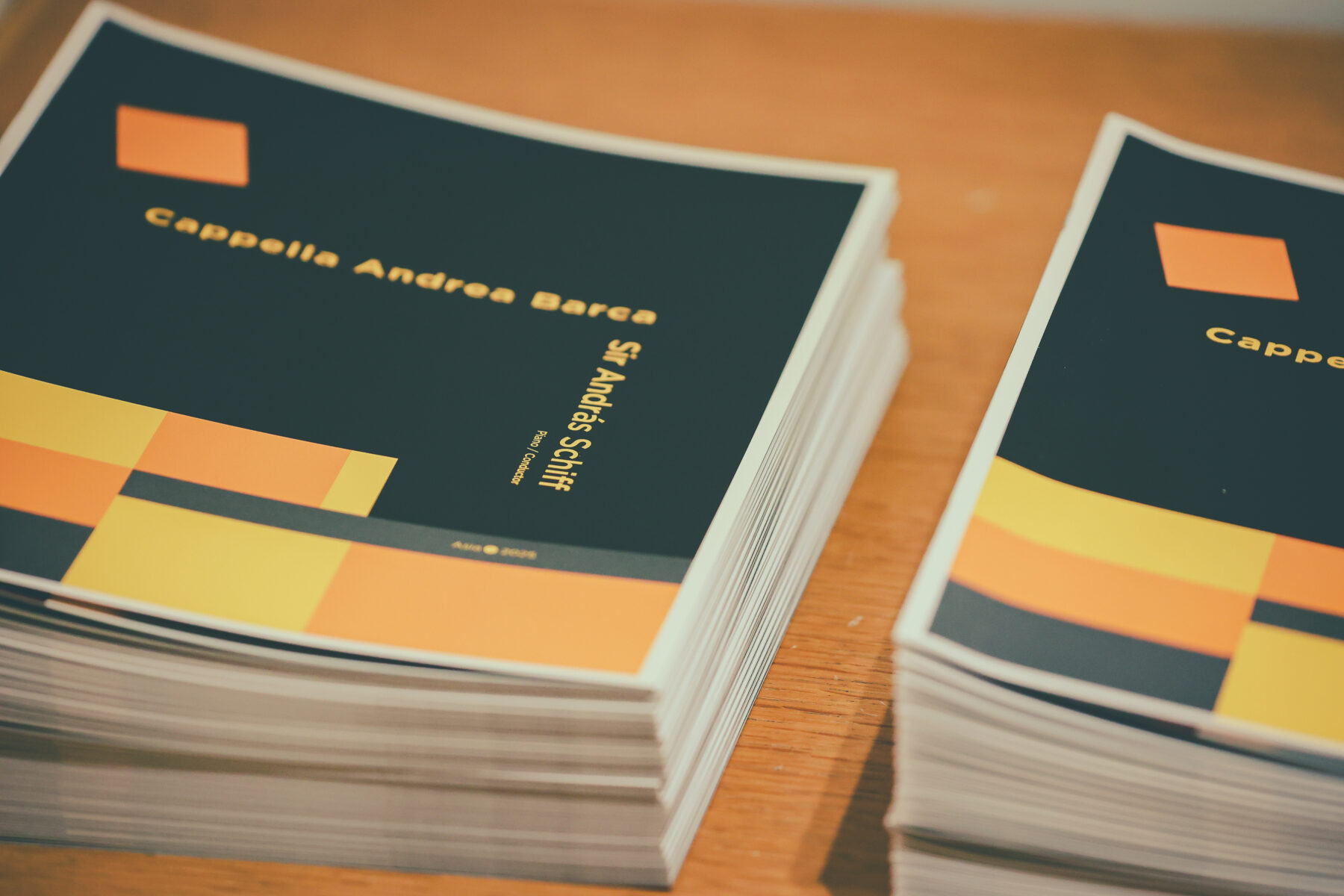
ところで前回のレポで「仲間を集めたほかのフェスティバル・オーケストラとは違って…」と書きました。これは会場で販売したプログラム冊子を読んでいただいた方にはおわかりいただけるかと思うのですが(特に音楽評論家の那須田務さんがお書きになったエッセイ)、言ってみればCABは「ヴェーグ・キネン・オーケストラ」?
彼らはシフたちの師でもあったヴァイオリニストで指揮者、シャーンドル・ヴェーグの志した音楽を今に体現する集まりなのだ、ということに気づかされる2公演でした。そのアナログ的な親密さといい、民主的なポリフォニーを重視し、それが生む音楽の自由な広がり。そして何より演奏する喜びの姿!
さらにヴェーグだけではなく、その中欧には同じく彼らが影響を受けた巨匠ラファエル・クーベリックやルドルフ・ゼルキンらがおり、彼らの志向したものでもあったでしょう。加えて、コンサートマスターのへーバルトはあのニコラウス・アーノンクール率いるウィーン・コンツェントゥス・ムジクスのコンマスをしていたわけで、弦パートに時折聴こえる古楽的な奏法はあくまで手段であって目的ではなく、音楽をポリフォニックに透明に響かせる力になっていたのだと思います。

そういえば、交響曲第40番の演奏のとき、コンツェントゥス・ムジクスがかつて最後の日本公演で「ハフナー交響曲」をやった時の残滓が。美しく艶麗であっても、ウィーンという楽都のほこりっぽい路地を歩いていたモーツァルトの、リアルな息遣いが感じられる気がしたのは私だけでしょうか?
だいぶ話が逸れてきてしまいました・・・。
今回のシフ&CABは、かつてヨーロッパの精神文化の中心にあったものを取り戻し、それを通じて音楽の深いところをたっぷり届けてくれた人たちであることを、この上なく実感させてくれたように思います。もちろんバッハとモーツァルトの音楽そのものと共に。自由と愉悦とともに。
そしてこれらの公演を聴いていただいた大勢のお客さまには心から感謝です。

*本記事に使用している写真は3月26日(水)東京オペラシティ コンサートホール公演にて撮影したものです